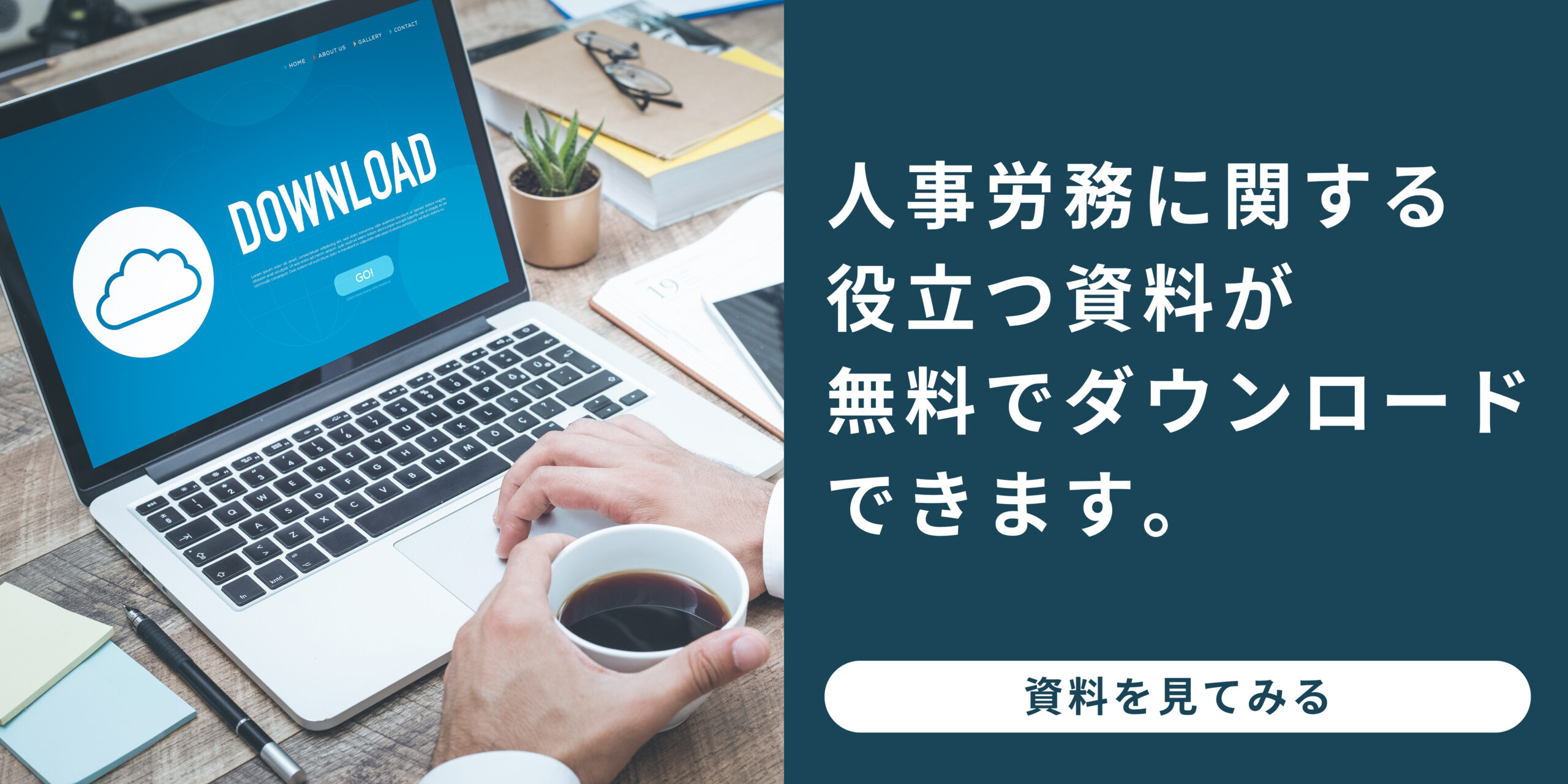女性が活躍できる会社へ!賃金差をなくす手順

1.はじめに
男女間の賃金格差は、中小企業経営者にとって避けて通れない課題です。多様な人材が活躍できる会社を目指す経営者にとって、賃金格差を放置することは、企業の競争力や従業員の働きがいを低下させるリスクにつながります。この記事では、具体的な原因や取組方法、活用できる支援ツールを分かりやすく解説します。ぜひこの記事を最後までお読みいただき、自社の状況を客観的に分析し、格差解消への第一歩を踏み出しましょう。
2.男女間の賃金格差の現状と推移
2-1.日本における男女間賃金格差の現状
日本では依然として男女間の賃金格差が大きいことが課題となっています。令和5年のデータによると、一般的な労働者の賃金を男性100とした場合、女性は74.8で約7割にとどまっています。この数字は改善傾向にあるものの、依然として男女差が明らかです。中小企業経営者としては、この現状を客観的に把握することが、対策を打つための第一歩となります。
2-2.国際的に見た日本の位置付け
国際比較で見ると、日本の男女間賃金差異は欧米の先進諸国に比べても特に大きい状況です。例えば、スウェーデンやフランス、イギリスに比べて日本の男女間格差は明らかに広がっています。これは日本の女性活躍推進の遅れや、企業における雇用管理の在り方に問題があることを示しており、経営者としての取り組みが急務です。
3.男女間賃金差異が生じる原因とは?
男女間賃金差異が生じる主な原因には、管理職比率の男女差、勤続年数の男女差、コース別雇用管理の運用方法などがあります。特に管理職比率については、日本企業において女性が管理職に就く割合が極端に低く、女性の賃金が相対的に低く抑えられる要因になっています。また、男女の勤続年数の違いも影響しており、出産や育児、介護などライフイベントを迎える女性は、継続的にキャリアを積みにくい状況があります。さらに、男女別の雇用管理コースが設定されている企業では、女性がキャリアアップの機会から遠ざかる傾向があり、それが直接的な賃金格差を拡大させる要因となっています。企業としては、こうした原因を把握した上で制度の再構築や運用改善を進める必要があります。
4.女性活躍推進法に基づく中小企業の義務とは?
4-1.常時雇用労働者101人~300人の事業主の場合
101人から300人までの企業には、「女性の活躍に関する現状把握」「数値目標を定めた行動計画の策定」「労働局への届出」「活躍状況の情報公表」が義務付けられています。自社の課題を正確に把握し、具体的な目標設定を行うことで、改善が促進されます。
4-2.常時雇用労働者100人以下の事業主の場合
労働者が100人以下の事業主には、同様の取り組みは努力義務とされています。しかし、情報を公開し自社の状況を積極的にアピールすることで、採用力向上や企業ブランドの強化に繋がります。
5.男女間賃金格差解消のための雇用管理制度の見直し
男女間の賃金格差を是正するためには、企業内の雇用管理制度を全面的に見直す必要があります。まず、賃金制度を公正で透明なものに整えることが重要です。賃金決定の基準を明確にし、役割や職務内容に応じて適切に評価する仕組みを導入しましょう。評価制度についても同様に、公平性・透明性が確保されるよう評価基準を明確に設定し、その内容を社員にしっかりと説明します。評価者に対する研修を定期的に実施し、評価のブレを最小限に抑える努力も必要です。さらに、昇進や昇格の基準を明確に定め、男女が平等に昇進機会を得られる仕組みを構築します。こうした制度見直しにより、従業員が納得して働ける職場環境が実現し、結果的に企業全体のモチベーションと生産性の向上につながります。
6.男女間賃金格差解消に向けた雇用管理運用のポイント
男女間の賃金格差解消を進める上で、実際の雇用管理の運用面に注目することが大切です。特に女性の配置や職務機会の均等化を徹底し、性別による不公平な待遇を排除する必要があります。採用時点から女性にも平等に挑戦の機会を提供し、重要なポジションへの配置を積極的に検討しましょう。また、育児や介護などライフイベントを理由とした不利益な配置転換を防ぐことも重要です。さらに、コース別雇用管理においても、性別でキャリアパスが固定されないよう注意し、従業員一人ひとりが自身の能力を最大限に発揮できる環境整備を進めましょう。
7.ポジティブアクションの推進による格差解消
ポジティブアクションとは、男女間の賃金格差や管理職比率の不均衡を解消するため、企業が自主的に行う積極的な取り組みのことを指します。特に、女性が管理職などの重要なポジションに就く機会が少ない場合、この施策を活用することで女性のキャリアアップを促進できます。
企業がポジティブアクションを推進する上で具体的に検討すべき施策には、女性向けの研修やキャリア開発プログラムの実施、昇進基準の見直し、昇進候補者の中から女性を優先的に登用することなどが挙げられます。これらの取り組みは単なる女性支援にとどまらず、企業内の人材活用を広げることで全体の生産性や企業イメージの向上にもつながります。
さらに、企業に根強く残る固定的な男女役割分担意識を見直すことも重要です。社内の研修や意識啓発活動を実施することで、男女が平等に活躍できる企業文化を形成しましょう。研修の具体的な内容としては、性別役割分担意識を見直すためのワークショップや、男女間格差の実態を社員全体で共有し議論する場を設けるなどが有効です。
また、企業がこのポジティブアクションを行っていることを積極的に外部に発信することも重要です。男女平等に積極的に取り組む姿勢を明確に示すことによって、就職活動中の求職者や社会からの評価を高め、結果的に優秀な人材の獲得や社員の定着にも効果を発揮します。
8.男女間賃金差異の「見える化」推進ツールの活用法
男女間賃金差異の実態を客観的に把握するためには、厚生労働省が提供している「男女間賃金差異分析ツール」が非常に役立ちます。このツールを活用すると、自社の男女間賃金差異がどのような要因で発生しているか、同業他社との比較も含めて具体的に分析することが可能です。また、付属するパンフレットや支援マニュアルを併用することで、現状把握だけでなく課題分析や具体的な行動計画の立案に繋げることができます。ツールを通じて自社の状況を具体的な数字で把握することで、課題解決に向けた有効な取り組みを進めることが可能となります。
9.まとめ
男女間賃金格差の解消は企業の社会的責任であると同時に、企業競争力を高めるための重要な施策です。本記事で示した賃金制度や評価制度の透明性向上、雇用管理の運用面での見直し、ポジティブアクションの推進を通じて、男女が公平に評価され、安心して働き続けられる環境が整います。その結果として従業員のモチベーション向上、優秀な人材の確保・定着、生産性の向上につながります。今すぐ具体的な一歩を踏み出し、男女が共に活躍できる職場環境の実現を目指しましょう。この記事で示した手法を実践することで、自社の課題が明確になり、改善の道筋が見えるようになります。ぜひ継続的にPDCAサイクルを活用しながら、男女が公平に評価される透明性のある企業を目指してください。
投稿者プロフィール

-
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。
最新の投稿
 三代目のブログ2025年4月1日女性が活躍できる会社へ!賃金差をなくす手順
三代目のブログ2025年4月1日女性が活躍できる会社へ!賃金差をなくす手順 三代目のブログ2025年3月1日2025年4月開始!育児時短就業給付金:中小企業経営者が知っておくべきポイント
三代目のブログ2025年3月1日2025年4月開始!育児時短就業給付金:中小企業経営者が知っておくべきポイント 三代目のブログ2025年2月1日法令違反を回避!SNSでの正しい求人情報の出し方
三代目のブログ2025年2月1日法令違反を回避!SNSでの正しい求人情報の出し方 三代目のブログ2025年1月1日令和6年改正育児・介護休業法を完全解説!中小企業が取るべき対応策
三代目のブログ2025年1月1日令和6年改正育児・介護休業法を完全解説!中小企業が取るべき対応策