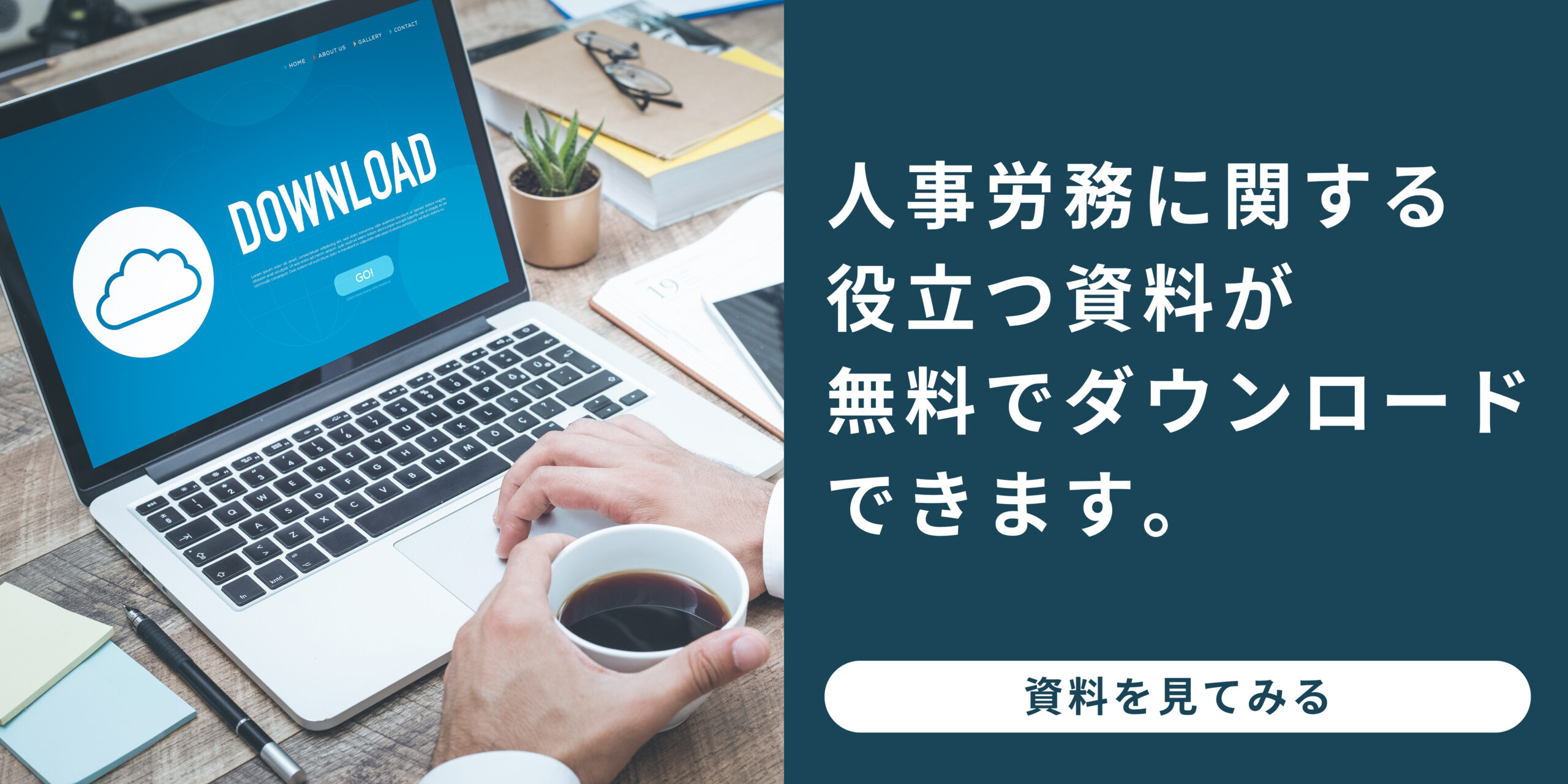2025年4月開始!育児時短就業給付金:中小企業経営者が知っておくべきポイント

1.はじめに
育児と仕事の両立は、従業員とその家族にとって重要な課題です。特に中小企業においては、人材確保の観点からも、育児をサポートする制度の充実が不可欠です。今回は、2025年4月から開始される「育児時短就業給付金」について、中小企業の経営者の皆様に知っておいていただきたい内容をまとめました。この給付金を活用することで、従業員の育児を支援し、企業の活性化にも繋げることが可能です。ぜひ、最後までお読みください。
2.育児時短就業給付金とは?
2025年4月1日から新たに創設される育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業する従業員を支援するための給付金です。育児期の従業員が直面する経済的な負担を軽減すると同時に、企業が育児と仕事の両立を支援しやすい環境を整えることを目的としています。この制度は、育児休業からの円滑な職場復帰を促進し、従業員の継続的なキャリア形成を支援することを目的としています。中小企業にとって、優秀な人材の定着は重要な課題であり、この給付金制度を積極的に活用することで、従業員の満足度向上や企業イメージの向上に繋げることが期待されます。
3.支給対象者
育児時短就業給付金の支給を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。対象となるのは、2歳未満の子を養育するために、週所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者です。ここでいう「被保険者」とは、雇用保険の一般被保険者と高年齢被保険者を指します。
さらに、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した、あるいは育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月以上あることが要件となります。過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、その後の期間に限られます。育児時短就業開始日前2年の間に、疾病、負傷、出産、育児などやむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間がある場合は、その期間を2年に加算できます(最長4年間)。
加えて、以下のすべての要件を満たす月について支給されます。
•初日から末日まで継続して被保険者であること
•1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間があること
•初日から末日まで継続して育児休業給付または介護休業給付を受給していないこと
•高年齢雇用継続給付の受給対象となっていないこと
月の途中で離職した場合や、週所定労働時間が20時間未満の場合は、原則として支給対象となりません。ただし、短縮後の1週間当たりの所定労働時間が20時間を下回る場合でも、子が小学校就学の始期に達するまでに週所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則などの書面により確認できる場合は、雇用保険の被保険者資格を喪失しないため、育児時短就業給付金の支給対象となる可能性があります。
4.給付額の計算方法
育児時短就業給付金の支給額は、原則として**育児時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%**です。ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように、支給率が調整されます。
育児時短就業開始時の賃金月額には上限と下限があり、2025年7月31日までの額は上限額が470,700円、下限額が86,070円です。育児時短就業給付金には支給限度額があり、2025年7月31日までの額は459,000円です。支給額が2,295円を超えない場合は、育児時短就業給付金は支給されません。これらの金額は、2025年7月31日までの額であり、毎年8月1日に改定される可能性があります。
具体例を挙げると、育児時短就業開始時賃金月額が300,000円で、支給対象月に支払われた賃金額が200,000円の場合、支給率は10%となり、支給額は20,000円となります。一方、支給対象月に支払われた賃金額が280,000円の場合、支給率は約6.43%となり、支給額は18,004円となります。また、育児時短就業開始時賃金月額が470,700円(上限額)で、支給対象月に支払われた賃金額が420,000円の場合、支給率は10%となりますが、支給限度額を超えるため、支給額は39,000円となります。
5.支給対象期間
育児時短就業給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月について支給されます。この各暦月を「支給対象月」といいます。ただし、以下のいずれかの日に該当する場合は、その日の属する月までが支給対象月となります。
•育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
•産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
•育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日
•子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日
たとえば、4月21日に育児休業から復帰と同時に時短就業を開始した場合、4月から翌年3月までが支給対象月となります。また、3月16日に別の子について育児時短就業を開始した場合、子Aの育児時短就業は2月までが支給対象月となり、子Bの育児時短就業は3月から支給対象月となります。
6.申請手続きの流れ
育児時短就業給付金の支給を受けるためには、事業主が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認、支給申請を行う必要があります。
①育児時短就業開始時賃金の届出
原則として、育児時短就業開始時賃金の届出が必要です。必要な様式は「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」です。ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、届出は不要です。
②受給資格確認
受給資格の確認を行います。必要な様式は「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」です。
③支給申請
原則として、2か月分の支給対象月をまとめて申請します。必要な様式は「育児時短就業給付金支給申請書」です。
被保険者本人が希望する場合は、被保険者本人が受給資格確認、支給申請を行うことも可能です。ただし、育児時短就業開始時賃金の届出は、事業主が行う必要があります。
7.企業が育児時短就業給付金を活用するメリット
育児時短就業給付金を活用することで、企業は以下のメリットを享受できます。
•優秀な人材の確保
育児を支援する制度を充実させることで、従業員の満足度を高め、離職を防ぎ、優秀な人材を確保することができます。特に中小企業においては、人材の確保が経営の重要な課題の一つであるため、育児支援制度の充実は企業の競争力強化に繋がります。
•企業イメージの向上
育児支援に積極的に取り組む企業として、社会的評価を高めることができます。企業の社会的責任(CSR)が重視される現代において、育児支援への取り組みは企業イメージ向上に大きく貢献します。
•生産性の向上
育児と仕事の両立を支援することで、従業員のモチベーションを高め、生産性の向上に繋げることができます。育児中の従業員が安心して働ける環境を整備することで、業務に集中できるようになり、結果として企業全体の生産性向上に繋がります。
•助成金・給付金との連携
育児支援制度を導入する際には、育児休業給付金や出生時育児休業給付金などの関連する助成金・給付金を活用することで、企業側の経済的な負担を軽減できます。
8.まとめ
今回は、2025年4月から開始される「育児時短就業給付金」について解説しました。この給付金は、従業員の育児を支援し、企業の活性化にも繋がる重要な制度です。中小企業の経営者の皆様におかれましては、この制度を積極的に活用し、従業員とその家族が安心して働ける環境づくりを進めていただきたいと思います。この記事が、皆様の企業経営の一助となれば幸いです。育児支援制度の導入は、従業員満足度を高め、企業全体の成長を促進する有効な手段です。ぜひ、この機会に育児時短就業給付金の活用をご検討ください。
投稿者プロフィール

-
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。
最新の投稿
 三代目のブログ2025年4月1日女性が活躍できる会社へ!賃金差をなくす手順
三代目のブログ2025年4月1日女性が活躍できる会社へ!賃金差をなくす手順 三代目のブログ2025年3月1日2025年4月開始!育児時短就業給付金:中小企業経営者が知っておくべきポイント
三代目のブログ2025年3月1日2025年4月開始!育児時短就業給付金:中小企業経営者が知っておくべきポイント 三代目のブログ2025年2月1日法令違反を回避!SNSでの正しい求人情報の出し方
三代目のブログ2025年2月1日法令違反を回避!SNSでの正しい求人情報の出し方 三代目のブログ2025年1月1日令和6年改正育児・介護休業法を完全解説!中小企業が取るべき対応策
三代目のブログ2025年1月1日令和6年改正育児・介護休業法を完全解説!中小企業が取るべき対応策